 |
|
|
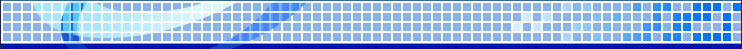 |
 |
|
|

|
本邦における人工視覚の研究は,厚生労働省と経済産業省の連携国家プロジェクトとして,2001年からスタートしました.目標は,網膜刺激型電極(人工網膜)による人工視覚システムを開発し,2010年までに臨床応用を目指すことです。発足当初は具体的な目標として、2006年に目の前30cmの距離で指の数が分かる視力(指数弁)の人工視覚を,動物実験で実現することでした.その後、プロジェクトは順調に進み、当初の目標より早く2005年には動物モデルでの視覚誘発と中期安全性を確認できました。その結果を踏まえ、2005年9月には網膜色素変性のボランティア2名による急性試験が施行され、視覚誘発の確認と2点弁別の可能性が示されました。更に解像度改善と実用機に向けた耐久性の最終調整を進めてきました。そして、実用機に搭載される刺激電極を用いた第2回急性臨床試験が2008年2月に行われ、動きのある視覚情報を伝えることのできる可能性が示されました。現在、長期の安全性の確認と実用機の完成に注力するとともに、将来に向け更に効果的な電極の開発を進めています。視細胞は失われていても,網膜の内層が残った状態であれば,人工網膜で視力回復する可能性があります.進行した網膜色素変性,自己免疫網膜症などが当面対象となりますが,研究が進めば加齢黄斑変性などにも適応が拡大します.
|

 |
2001年
・NEDO (新エネルギー・産業技術総合開発機構)の
人工視覚システム5ヵ年プロジェクト開始(リーダー:田野保雄)
・厚生労働省「網膜刺激型電極による人工視覚システムの開発」
(研究代表者:田野保雄)
2003年
・NEDOプロジェクト中間評価
2005年
・網膜色素変性患者での急性臨床試験(2点弁別可能)
2006年
・NEDO 「人工視覚システム実用化のための研究開発」プロジェクト開始
| |
 |
|
|
 |
| このホームページでは、人工視覚に関していくつかの用語が用いられています。人工視覚またはartificial
visionは「人工的に得られる視覚」一般を、人工網膜またはartificial retina, retinal
chipは「網膜を刺激することにより人工視覚を得ようとするシステム」を、人工眼またはartificial
eyeは「網膜、視神経、大脳皮質のいずれかを刺激して人工視覚を得ようとするシステム」を指します。
|
| |
 | |
 |