 |
|
|
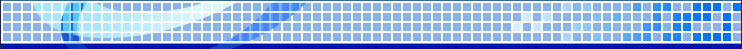 |
 |
|
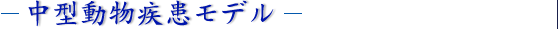

人工網膜の動物実験では、人に近い眼の大きさを持った動物に人工網膜を移植する実験が必要になります。この場合、単に人工網膜の安全性のみを評価したいのであれば正常の動物に移植すればよいのですが、実際に失明した患者様に視力を再び与えるという目的を考えた場合、失明した動物に移植して視力が向上したことを証明することが必要になります。この場合、視細胞に重度の障害を持ちながら、視神経機能はまだ保たれているというような動物モデルでなければいけません。我々は、様々な方法を用いて中型動物(主にウサギ)の視細胞変性による失明モデル動物作成の実験を行ってきました。
特に遺伝子操作による視細胞変性モデルを作成する試みは、現在我々が最も重点をおいている方法です。これは、実際に網膜色素変性の原因遺伝子の一つであるロドプシン遺伝子の変異をウサギに導入するというものです。ウサギのロドプシン遺伝子を含むゲノムクローンを単離して、実際に網膜色素変性の原因となる遺伝子変異の一つ(Pro347Leu変異)を導入したベクターを構築し、これを高純度に精製してウサギ受精卵に注入します。このような遺伝子操作による網膜色素変性モデルは、これまでマウス、ラット、ブタで成功していますが、ウサギでは世界で初めての試みです。
我々はこのトランスジェニックウサギの作成を繰り返し行ない、その結果合計10匹のファウンダー作成に成功し、そのうち6ラインの系統を樹立しました。このウサギは、生後1か月の時点で既に明らかに視細胞変性が始まっており、生後約1年では網膜電図でほとんど杆体成分の反応が消失することがわかりました。この時点ではまだ錐体機能は残存しており、この網膜変性の様式が実際の網膜色素変性患者のそれとよく類似していることが証明されました。今後は、さらに6つのライン全てにおける網膜変性の過程を詳細に調べ、その後にこのウサギモデルに実際に人工網膜の移植を行なう予定です。
|
| |
 | |
 |